年末になると親子の間で会話の中心になるサンタさん。
「サンタさんは良い子のところに来るんだよ!」なんて私もよく5歳の息子に言っています。
子どもたちがサンタさんの正体に気付くのはいつなのでしょうか?
サンタさんの正体がどうばれてしまうのか、どんなふうに親がばらすのか調べてみました。
サンタさんの正体のばらし方

小学校の中学年くらいで親の方から、「サンタさんはパパなんだよ」と伝えるという家庭もあるようですが、無理に親から伝える必要はないと考える人もいて、どうするのがいいかに正解はないと思います。
子どもなりの解釈を聞いてあげる方法
もし子どもに聞かれたら、子どもがどうしてそう思うのか解釈を聞いてあげると良いという専門家もいました。
疑問を持つということは、それだけ思考が現実的になり、成長した証だからだそうです。
サンタからの手紙で察してもらう方法
あるご家庭では、親がサンタさんからの手紙を書いて子どもに察して貰うようにしているとか。
「君よりも小さな子どもたちにプレゼントを配るのが増えてしまったから、来年からはパパとママにバトンタッチするよ。今までありがとう。サンタより」
と書いて、プレゼントと一緒に置いておくそうです。
子どもがもらう側から与えるサンタ側になる方法
海外の方法で有名なのは、子どもたちがサンタからプレゼントを受け取る立場から、子どもがサンタになる「サンタミッション」をするというものです。
子どもがプレゼントを渡す自分の周りの人を選んで、プレゼントを探しラッピングして、そっと置いておくとのこと。
貰う側を卒業して、今度は与える側になるそうです。
誰かをワクワクさせる側になるというのは面白いですよね。
サンタの起源を伝える方法
サンタクロースという存在には始まりがあって、それを伝えるという方法もあると思います。
実際にフィンランドのラップランドのサンタ村の存在を教えてあげるのも良いですよね。
サンタの起源
サンタのモデルとなった聖ニコラウスは、不幸な人々を助けるために様々な奇蹟を起こす存在として言い伝えられました。
貧困のため、身売りする予定だった娘の家の煙突へ金貨を投げ入れ、その一家を助けたそうです。
この伝説が、サンタのストーリーの原型だそうです。
私の子どもの頃の場合
因みに私自身がどうだったかと言うと、あまりプレゼントの習慣のない家だったので、「サンタからのプレゼント」と言われたことは恐らくありませんでした。
クリスマスになるとプレゼントを貰える友達が羨ましくて、お願いして寝ている間にプレゼントを置いて貰った記憶があります(可哀想!)。
サンタの存在についても、小学生のときに父に「サンタさんっているの?」と聞いたら、とっても現実的な返事が返ってきました。
「伝説みたいなもんだが、実際にモデルはいるらしいよ。聖ニコラウスというんだ。現代では、フィンランドのラップランドっていうところにサンタ村というのがあって、そこにサンタがいるそうだ。」
と詳しくは覚えていませんが、父の持ってるサンタのウンチクを教えてくれました。
子どもながらに「ラップランドに行って会ってみたい」とその時思ったのを覚えています。
私はサンタを信じる信じないの前に、あまりサンタが身近ではなかったという感じです。
これを夫に話したら、「なんて夢のない…」と憐まれてしまいました。
サンタさんの正体に気付くのは何歳?

何歳くらいまでサンタさんを信じているかについても調べました。
クリスマスの日にプレゼントを置いていくのが、本当にサンタなのか子どもが気付くのは、5歳以降だそうです。
イギリスの調査では、6歳までに30%以上の子が気付くとのこと。
だんだんと増えていき、小学校高学年では大半の子どもがサンタの存在に気付いているそうです。
サンタをいつまで信じていたかのアンケート調査
いつまでサンタを信じていたかを調べたアンケート調査を探してみました。
子どもとのお出かけ情報サイト「いこーよ」の調査
信じていた年齢の割合
- 6歳 サンタクロースを信じる割合がピーク
- 10歳以降 信じる割合が5割以下
日本の雑誌社のアンケート結果
何歳まで信じていたか
- 1位 小学校の中学年(9−10歳)
- 2位 小学校低学年(7−8歳)
- 3位 幼稚園・保育園の年中・年長(5−6歳)
日本の発達心理学の大学教授の調査
年齢別でサンタをどの程度信じているか
- 3ー4歳 大体の子どもがサンタを信じている。見かけの扮装を信じるので、サンタの格好をしているからサンタに違いないと思う。
- 5ー6歳 サンタの格好をしているけど、ただのおじさんがサンタの格好をしているだけなのかもしれないと物事を多面的に見られるようになる。
- 小学校1年生 まだまだ大体の子どもがサンタを信じている。
- 小学校3年生 急にサンタを信じる子どもが減る。一晩で世界中の子どもにプレゼントを配れるわけない。どうやって空を飛ぶ?家の鍵が掛かっているのにどうやって入る?と論理的に考えられるようになる。
子どもが気付くのはどんなとき?
子どもたちはどんな時にサンタの存在に気づくのでしょうか?
- 親がプレゼントを置くところを見られる
- 友達やきょうだいに聞く
- 自分で考えて気付く
やはり、友達同士の会話の中で知ることが多いようです。
サンタさんからの卒業は心の成長の証ですね。
親がプレゼントを置いているところを見られてしまっては、もう言い逃れ出来ませんね!
私も子どもの施設に勤めている時に、寝ている子どもの枕元にプレゼントを置いて回りましたが、「先生が置いたでしょ?」と中学生の子に言われました。子どもは暴く気満々でしたが、「いやいや、先生が見回り来る前からあったし!」と年少児の手前、しらを切り通しました。笑
サンタさんからのプレゼントを止めるのはいつ?
大体の親が、子どもが小学生のうちにサンタからのプレゼントをやめているそうです。
子どもたちがサンタを信じなくなったらやめるということですね。
信じていないのに、無理にサンタさんからと言う必要もないですよね。
まとめ
子どもたちの大好きなサンタさん。
子どもの成長に従って、その存在が子どもたちの中で変わっていくのは、寂しいような誇らしいような気持ちになりますね。
私の父のように、現実を最初から教えなくても良いとは思いますが…、子どもたちにとってのサンタさんがキラキラした優しい存在であって欲しいなと感じます。
サンタを信じていようとそうでなかろうと、クリスマスが子どもたちにとってわくわくする一大イベントであることには変わりませんね!
皆さまのクリスマスが楽しくステキな日であるよう、祈っております。
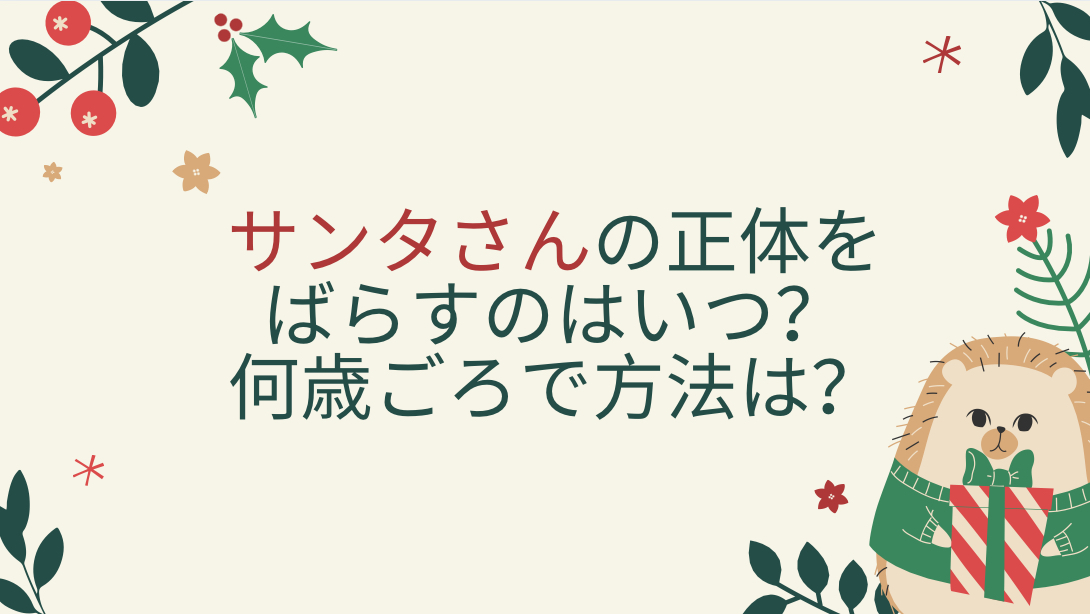
コメント